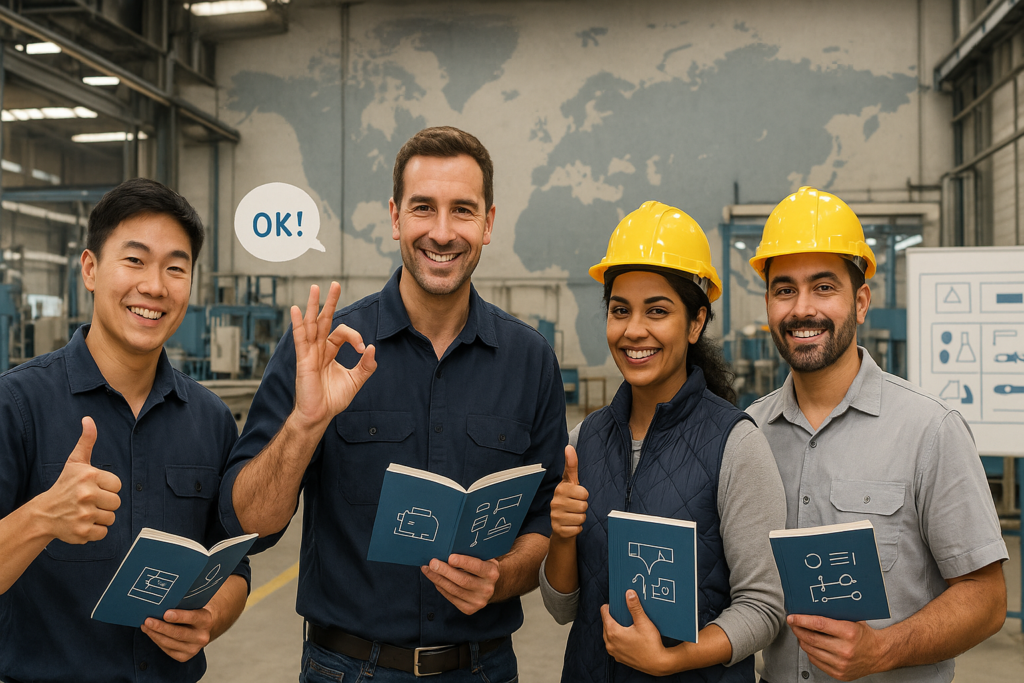製造業において、「品質をつくり込む」ためには工程管理だけでなく、「標準作業とその確実な実施」が不可欠です。その要となるのがマニュアルです。しかし、現場では「マニュアル通りにやっていない」「内容が古いまま」といった課題も少なくありません。
本記事では、品質保証部門で10年以上現場改善を主導してきたプロフェッショナルへのインタビューを通じて、「品質管理とマニュアル活用の理想的な関係」について実践的に解説します。
※本記事は、当社業務の実態をもとに構成した【仮想インタビューコンテンツ】です。登場人物・部署名などはすべて仮想のものです。
Q&Aインタビュー:品質保証部門の視点からマニュアル活用を考える
インタビュー対象者プロフィール
山口 拓也 氏(仮名)|製造業・品質保証部門 課長職(経験15年)
自動車部品メーカーで品質保証を中心に製造・検査・教育体系の整備を経験。マニュアルの刷新や監査対応の仕組み化に多数携わる。
Q1. 品質保証の視点で、マニュアルの役割をどう捉えていますか?
山口氏:
マニュアルは「品質を守るための前提条件」です。現場で安定した品質を維持するには、誰が作業しても一定の成果が出る標準作業の徹底が不可欠です。その標準を記録し、伝える手段がマニュアルです。
品質保証部門としては、作業ミスやばらつきが発生した際に「マニュアルに明記されているか?」「現場で使われていたか?」を必ず確認します。トラブルの再発防止策にもマニュアルが関わります。
[解説ポイント]
- マニュアルは「品質の前提条件」
- 不具合時の再発防止や是正処置にも活用
- 品質保証のPDCAにおいて「標準化・マニュアル整備」はP(計画)の一部として重要
Q2. 現場でマニュアルが形骸化してしまう原因は何でしょうか?
山口氏:
よくあるのは、「とりあえず作ったマニュアル」が現場で使われず放置されるケースですね。
その多くが、以下のような状態です。
- 現場作業者の視点が反映されていない(机上の内容)
- 更新されていない(実際の手順とズレがある)
- 必要な情報がどこにあるかわからない/読みづらい
また、「作業者が口頭で伝えてしまっている」場合も、マニュアルが使われない原因です。
[現場の声]
「マニュアルはあるけど、古くて使ってない」
「文字ばかりで見る気がしない」
「聞いた方が早いから、ベテランに聞く」
Q3. マニュアルを活用するために品質保証部門が工夫している点は?
山口氏:
私たちの現場では以下のような取り組みをしています。
- 現場との共同作成:マニュアルの改訂は、現場リーダーや作業者と一緒に行う
- フォーマット統一:図・写真を多用した見やすいテンプレートを採用
- マニュアルレビュー会の定例化:月1回、各工程のリーダーと改善点を確認
- 現場で使える形式にする:紙+タブレット両対応、検索性の向上
特に「現場巻き込み」が重要です。現場が納得し、自分たちの言葉で書かれていることが、マニュアルの浸透につながります。

Q4. 成功事例として印象に残っている取り組みはありますか?
山口氏:
新ライン立ち上げ時に、「マニュアル先行型の教育」を実施したことがあります。
従来は「ラインが動き出してから教育」でしたが、立ち上げ前に作業者全員がマニュアルをもとに訓練を受けた結果、初期不良率が従来比で60%減になりました。これが現場に「マニュアルの力」を実感させる良いきっかけになりました。
Q5. 最後に、読者へのアドバイスをお願いします
山口氏:
マニュアルは「管理のための資料」ではなく、「現場で使ってこそ意味があるもの」です。
品質を守るためには、作業の標準化が絶対に必要です。そのためには、現場目線で、使いやすく、そして常に更新されるマニュアルを維持することが不可欠です。
品質保証部門だけでなく、生産管理、現場リーダー、教育担当など全員でマニュアルの価値を共有していく文化が、結果として強い品質体制を作ります。
まとめ:マニュアルは品質管理の「武器」になる
- マニュアルは品質を支えるインフラである
- 現場目線のマニュアルづくりが鍵
- 形骸化させないためには、更新・教育・仕組みが不可欠
マニュアルは作って終わりではありません。品質と同じく、継続的な改善(KAIZEN)の対象です。
製造現場の品質向上には、「現場で活用されるマニュアル」が土台にあることを、今一度確認してみてください。
この記事を書いた人
編集部