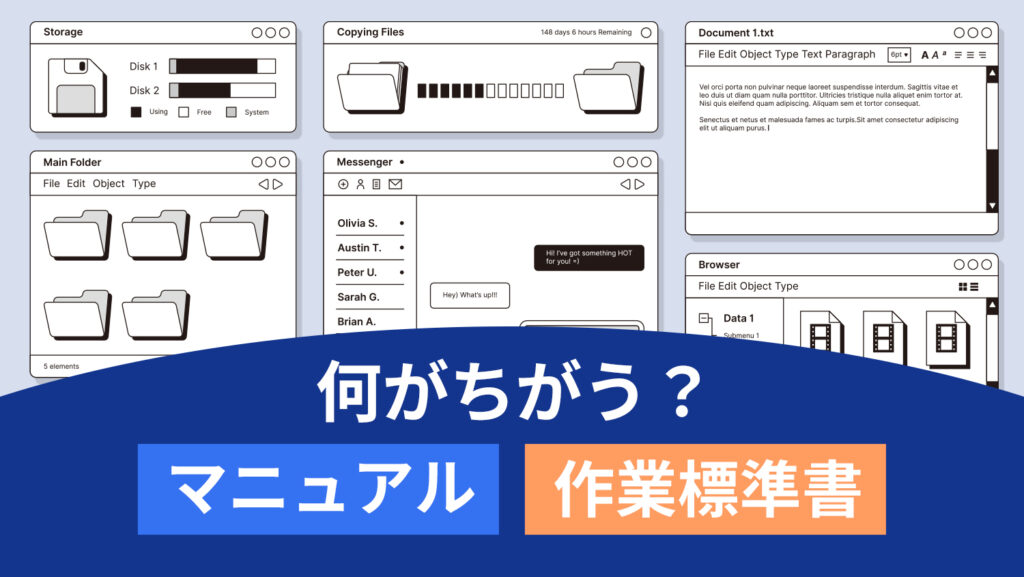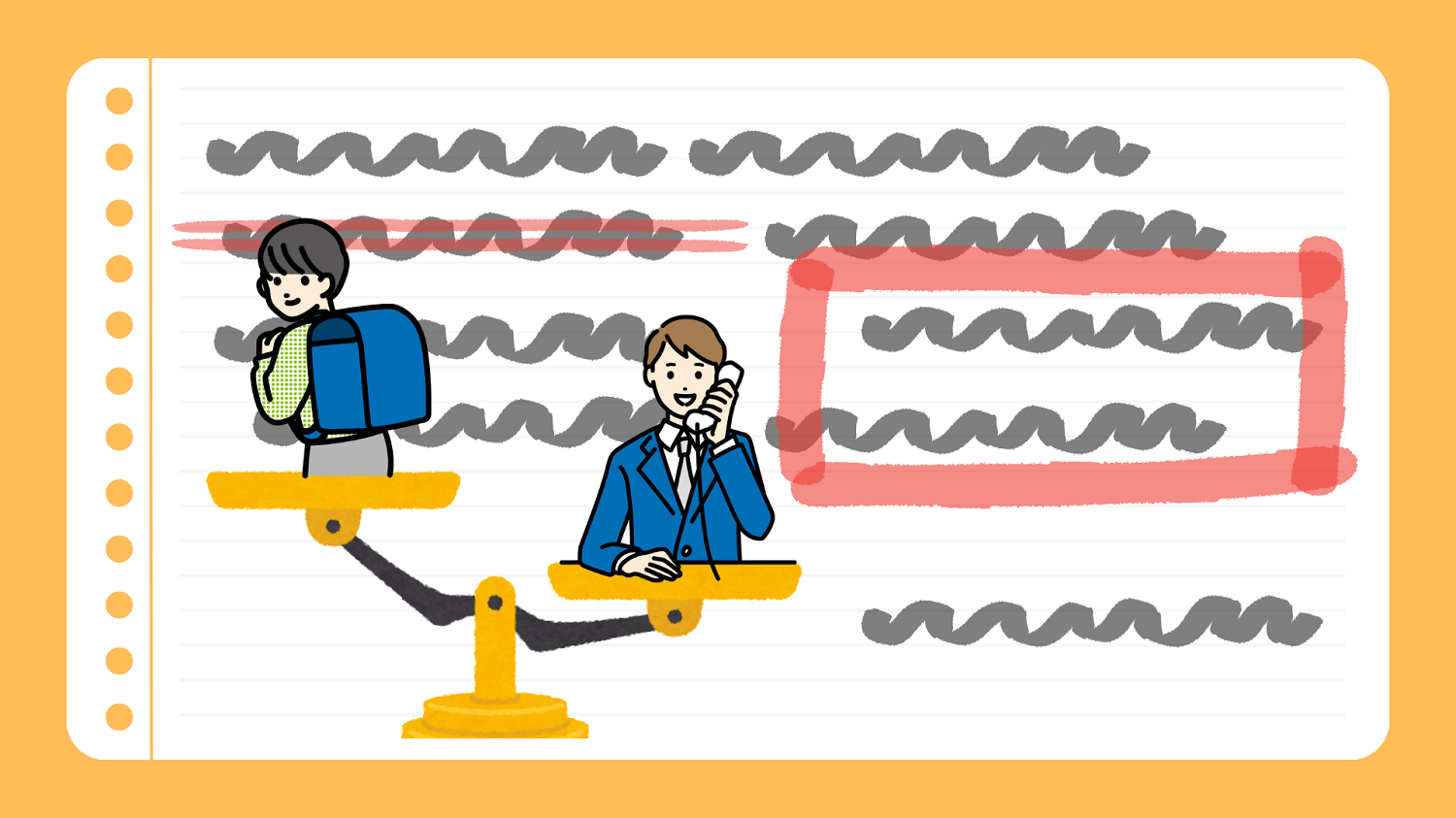
マニュアルに限らず、日本語の文章でよく出現する「並列表現」。文法的に同じ構造の内容を並べる表現方法で、長い文章にリズム感を持たせ、読みやすくすることができます。
しかし、「文法的に同じ構造」という点で、使用には注意が必要な表現方法でもあります。実際にマニュアルを読んでいても、異なる構造の要素が並べられているために意味が通らなかったり、複数の解釈が可能になり誤解の元となったりしている文が見受けられます。
今回の記事では、そんな「並列表現」にスポットを当て、マニュアルを作成する際にも注意したいポイントを解説します。
並列表現の代表2種と使い方
日本語の並列表現には様々な種類があり、文法や意味によって使い分けられています。ここでは、並列表現のうち、マニュアルでよく使われ、間違った使い方が見られるものをいくつかご紹介します。
1. 列挙する並列表現
特に意味を追加せず、単に2つの事柄を並べる表現です。
例えば以下のようなものが挙げられます。
- と
- および
- や
※実際には「や」には他の可能性を示す意味が含まれますが、ここでは「列挙」の一部として分類しています。
2. 選択肢を示す並列表現
2つの事柄を並べ、そのいずれかを選択する意味を追加する表現です。例えば以下のようなものが挙げられます。
- か
- または
3. 使い方の注意点
いずれの表現でも、使用する際は並列させる事柄が同じ構造であることがポイントです。
以下は、文法的に構造が異なる例です。いずれも文脈的に意味を想定することは簡単ですが、日本語として正確な表現にはなっていません。
誤った例
私の趣味は、読書と絵を描くことです。(言い回しの不統一)
大人の話し方と子どもには違いがあります。(文法構造の不統一)
正しい例
私の趣味は、本を読むことと絵を描くことです。
大人の話し方と子どもの話し方には違いがあります。
文法的にミスがあると、正しく理解されなかったり、翻訳を行う際に誤訳の原因となったりすることがあります。
誤解が重大な作業ミスに繋がる可能性もあるため、マニュアル作成時には正しい日本語の使用を心がけましょう。
並列表現と係り受け
並列表現を使用する際のポイントは「並列させる事柄が同じ構造であること」とお伝えしました。
実は、ここでの「構造」には、文法的な品詞や言い回しに加え、意味的な構造も含まれています。
並列表現には、文法構造や言い回しを統一していたとしても、あいまいな表現となってしまう場合があります。例えば、下記の文は実際に使われているマニュアルから抜粋したものです。
X軸とY軸に平行な2辺の中心座標と幅を計測します。
並列表現が1文中に2回使われており、しかも係り受けが不明確になってしまっている例です。
慣れている方だと難なく理解できるかもしれませんが、初めて読む人にとっては、理解するまでに少し時間を要する表現となってしまっています。
問題1:「平行な」が係る語句が不明確
まずは、前半の「X軸とY軸に平行な2辺」に注目します。
ここでの問題は、「平行な」がどの語句に係っているか不明確、という点です。
- 「X軸とY軸に平行」な2辺
解釈:X軸に平行な辺と、Y軸に平行な辺がある
- 「X軸」と「Y軸に平行な2辺」
解釈:X軸とは別に、Y軸に平行な辺が2つある
この問題は、並列表現と形容詞句が同じ文中で併用されており、使用している形容詞句が、意味的には並列させる語句のどちらにも係る可能性がある場合に起こります。
この問題を解消するには、無理に並列表現で短くまとめようとせず、説明の語句を追加するか、文を分ける必要があります。
問題2:「の」が係る語句が不明確
次に、後半の「2辺の中心座標と幅を計測」に注目します。
こちらも先ほどの問題と同様に、「2辺の」が係る可能性のある語句が複数並列されてしまっています。
- 「2辺の中心座標」と「幅」を計測
解釈:2辺の中心座標とは別に幅を計測できる箇所がある
- 2辺の「中心座標と幅」を計測
解釈1:2辺それぞれについて、中心座標と幅を計測
解釈2:2辺の中心点の座標、2辺間の幅を計測
このように、複数の解釈の可能性が生まれてしまいます。
マニュアルの読者は、熟練の作業者よりも初心者の方が多いはずです。作業に慣れない方が参照することを考え、誰にでも誤解なく伝わる表現を選択することが、誤作業の防止に繋がります。
マニュアル執筆時のチェックポイント
マニュアルの執筆にあたって、並列表現は避けては通れないものです。執筆する際やチェックを行う際、誤りに気が付くためのポイントをご紹介します。
1. 構造が統一されているか確認する
並べたい語句を抜き出し、同じ構造になっているかを確認します。例えば、以下のような状態になっていないでしょうか。
- 品詞が異なる(名詞と動詞など)
- 情報の大きさが異なる(部分と全体など)
該当する場合は、並べる語句が同じ構造になるように修正します。
2. 係り受けが明確になっているか確認する
文の主語に並列表現が使われている場合や、文中に形容詞句が含まれている場合は、複数の解釈が可能な文になっていないか確認します。もし複数の解釈が可能になっていた場合は、説明の語句を追加するか、箇条書き等を使用し、文を分けることをお勧めします。
目的語に並列表現が含まれている場合
「AとBを~する」というような文の場合、内容によっては複数の解釈が可能になることがあります。
上記の例では、「Aを~する」としても意味が成立するかどうかを確認します。
形容詞句が含まれている場合
「○○の(な)AやB」、のような形容詞句が含まれている場合は、確認したい形容詞句で「○○の(な)A」「○○の(な)B」の両方が成立する内容かどうかを確認します。
もし複数の意味が成立する内容となっていた場合は、1文として読む際、どちらに係る語句かが不明確になっている可能性が高いです。その場合は、言い回しを変える、読点を打つ、文を分ける等の工夫が必要です。
まとめ
並列表現は、日本語をライティングする上では欠かせない表現です。もちろんマニュアル内でも大量に出現しますが、同時に意味的・文法的ミスが起きやすい箇所でもあります。日本語のマニュアルをライティングする際は、なんとなく並列表現を使用するのではなく、不明確な表現となっていないか注意する必要があります。
並列させたい項目が多い場合は、文を分け、箇条書きにすることで、一目でわかる記載にすることができます。記載内容に合った表現方法を選択し、誤解のないマニュアルを目指しましょう。
★過去の「読みにくい日本語」シリーズ★
この記事を書いた人
編集部 Y