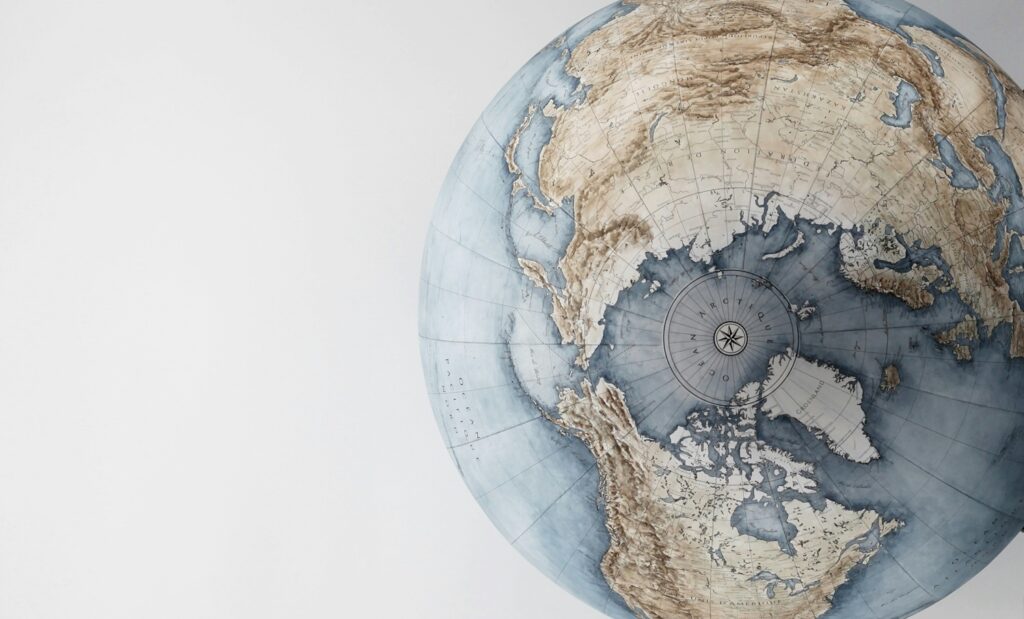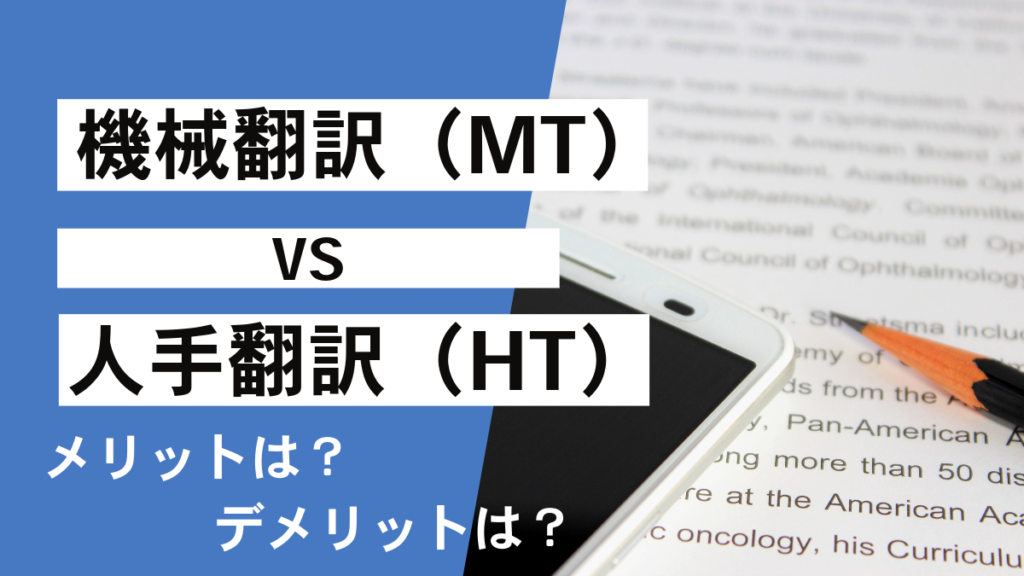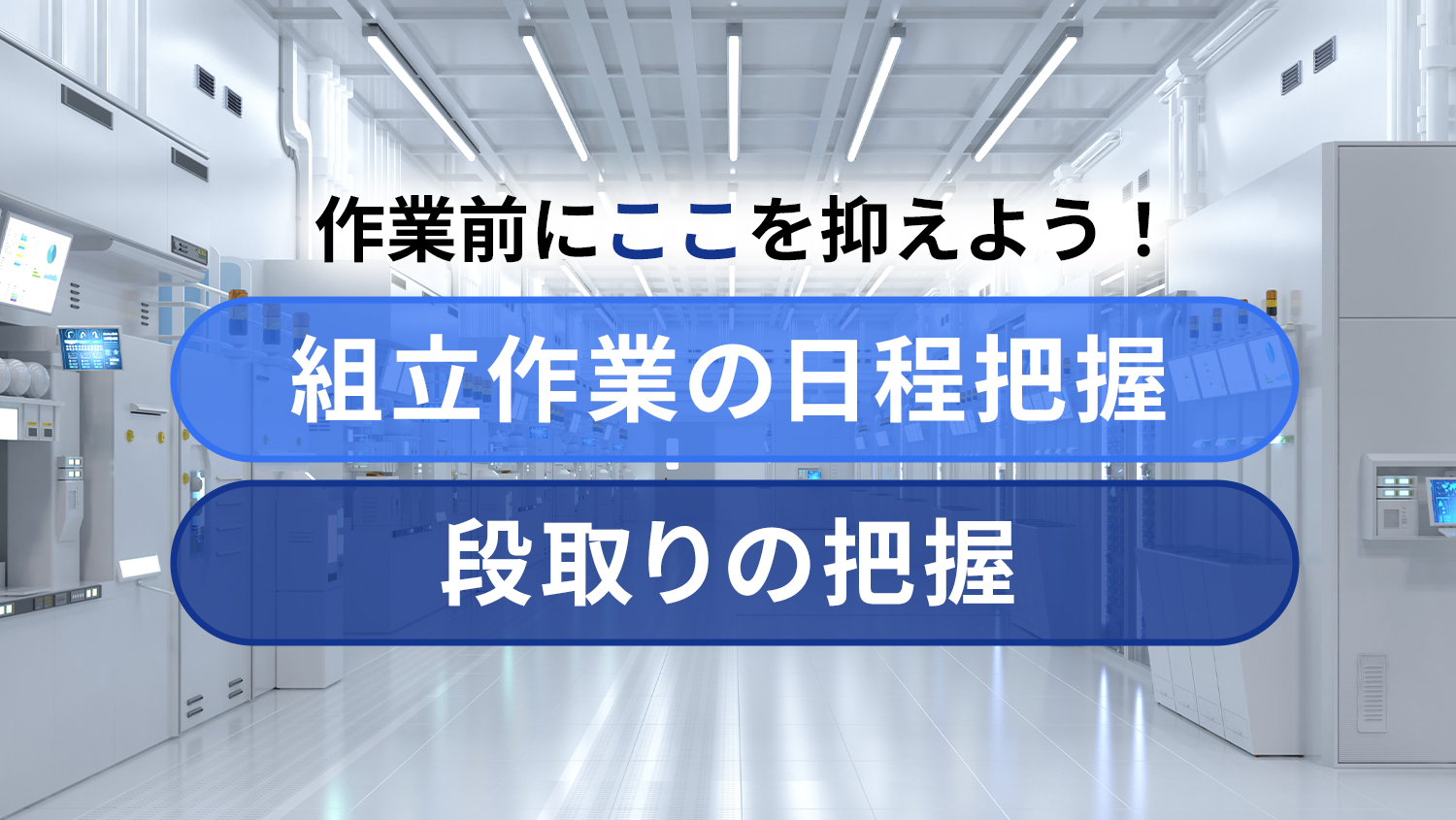
国際市場において競争が激しい製造業では苦戦している日本ですが、製造に必要な製造装置の評価は高く、国内外に出荷されている状況です。
しかし、製造業でもマニュアルで管理されているライン生産と、セル生産を行う製造装置の組立では、作業の進め方が異なります。そのため、下記のような問題を抱える製造現場もあるでしょう。
「現場任せの教育でマニュアルがない」
「やりながら見て覚えろって言われても...」
「出荷日までの段取りがわからない」
今回の記事では、現場で作業をはじめる前に覚えておきたい組立作業の日程に対する捉え方と、段取りを詳しく解説します。これから製造業に従事する予定の方や製造業企業に入ったばかりの方はぜひ参考にしてみてください。
最初は日程の把握が重要

最初に行うのは日程の把握です。日程管理は生産管理の仕事ですが、現場の作業者も下記6つの日程を把握しておきましょう。
- 部品納入日
- 組立開始日
- 配管予定
- 電気配線予定
- 装置の調整開始日
- 出荷日
一般的に、日程は職場のリーダークラスから聞きますが、生産管理部署からの情報と比べて差異がないかも確認します。日程は基本的なもので、順調にいくとはかぎりません。むしろ、遅れることを前提として考えておくことが必要です。
日程を計算する際には「部品納入日」からではなく「出荷日」からさかのぼって計算しましょう。
たとえば、〇月△日に出荷しなければならない場合、いつまでに調整が必要か確認します。電気配線を〇月□日から行うなら、いつまでに組立を終わらせるかを知る必要があります。
「部品納入日」から計算すると日程が遅れた際、予定が後ろ倒しになるだけでリカバリが難しくなります。理解するために、6つの日程を詳しく解説しましょう。
1. 部品納入日
部品の手配と納入日程を管理するのは、一般的に購買・調達部です。購買担当に聞くのは簡単ですが、購買の業務はシステム化されている場合がほとんどですので、社内システムから確認しましょう。人に聞くより早く、納入予定が変更された場合でもオンラインで確認できます。
大事なことですが、部品は納入されて直ぐに現場にくるわけではありません。まず、受け入れ部署が数量などを確認します。加工部品なら受け入れ検査を行う必要もあります。そのため、現場に届くのは数日後です。
製造装置の組立現場では、部品が1つないだけで作業が止まってしまいます。そうならないために、作業者は部品の納入日と現場までの詳細を把握しておきましょう。
2. 組立開始日
組立の開始前までに、必ず部品の構成図と組図を入手します。組図と一緒に小部品図面も付いているか確認しましょう。構成図と組図、小部品図面を照らし合わせ、差異がある場合は関係部署(生産管理か購買)に確認します。
部品の納入が遅れている場合でも、部品の重要度を組図から確認します。なくても他の部分が組立られるなら進め、作業が止まるようなら関係部署に相談して対応します。肝心なのは、部品の納入が遅れている現状を周知して、早く対応してもらうことです。
納入遅延は、作業者の責任ではありません。ですが、早く解決するためには迅速に連絡する必要があります。作業後半に苦労するのは作業者なので、事前に構成図や組図を把握して、いつでも対処できるようにしましょう。
3. 配管予定
配管作業は組立が終わらないとはじめられませんので、組立に関しては最初の山場となります。気を付けておきたいのは、配管に使用する継手や配管チューブの在庫です。毎回発注する部品とは異なり、少なくなったら都度発注する現場在庫です。
実際に、作業中に足りなくなる場合が多く、慌てる状況が多々あります。そのため、日頃から現場の在庫を注視して管理しましょう。毎週決まった曜日にチェックするなど、ルール化も重要です。
一般的に、配管部材は発注しても短納期で納入されます。ですが、数時間から数日間は作業が止まり、最後に苦労することになるため、注意が必要です。
4. 電気配線予定
一般的に電気配線は組立する作業者ではなく、専門の人員が行い、外注の業者に依頼する場合もあります。そのため、組立および配管は配線がはじまる前に終わらせなければなりません。
組立や配管が遅れても残業などでリカバリする方法があります。ですが、電気配線を依頼する業者には、決まった日程で作業を請け負っている場合が多く、終われば他の現場に行きます。急な日程変更の依頼は難しいので、配線日までに作業を終わらせましょう。
5. 装置の調整開始日
電気配線が終われば装置が動かせますので調整開始です。調整を終わらせたら出荷だと言いたいところですが、本当に厳しいのはここからです。一般的に、装置の出荷前には客先が現場にきて行う「立会い」があり、仕様書の確認があります。
立会い日までに調整を行い、仕様書に記載された条件を全てクリアする必要があります。クリアできなければ後日に再立会いなど、出荷が遅延する可能性があります。
6. 出荷日
立会いが終われば出荷ですが、正確な出荷日は立会い時に決まるのがほとんどです。出荷日が決まれば、特に大きな問題はありません。考えておくのは、当日の搬出経路です。大きな装置の場合、搬出経路を通れるか事前に確認する必要があります。
経路中に障害物があれば当日までに移動するなり対応しましょう。また、装置と共に同梱する部品や、工具をリスト化してチェックが必要です。
実際に、現地で部品や工具が足りなくなる状況はよく発生します。設置が海外だと目も当てられませんので、注意しましょう。
図面はどこからやってくる?

作業者にとって、一番重要なのは、構成図や組立図、部品図などの図面です。一般的に、図面は生産管理や購買など配布部署から現場に配布されます。しかし、覚えておきたいのは、設計や出図を指示するのは設計部だということです。
当たり前のことだと思うでしょうが、組立中には図面の間違いや、不明点など、多岐にわたる問題が随時発生します。流れからすると、図面を配布した部署に聞くのが一般的なので、配布部署である生産管理や購買に問い合わせします。
ですが、配布部署が確認する先は設計部がほとんどです。そのため、一番早く確実に確認する方法は設計者本人に直接確認する方法でしょう。あいだに人を介すると時間がかかり、間違った情報を聞く可能性もあります。
所属している組織では、配布部署に報告するのがルールかもしれません。その場合でも、最初は設計者とコンタクトをとってから配布部署に連絡する方法が早くて無難です。
最初の段取りができれば周りにも安心して見られる
装置組立の作業前に覚えておきたい日程と、段取りを解説しました。事前に日程プロセスを理解しておけば、精神的にも楽に作業できるでしょう。
段取りを考えながら整理された環境では、基本的な作業もスムーズに行えます。整理という基礎的なことも徹底してできるような人なら、なおのこと周りの同僚からも安心して見られ、信用も上がっていくでしょう。
信頼を得るためにも、スキルを磨き、日々しっかりと作業に取り組んでいってください。
この記事を書いた人
hiroyuki's
中国留学後、現地採用にて深セン勤務。帰国後は半導体製造装置メーカーや通信機器メーカーにて、購買、生産管理、組立、品質保証業務に従事。現在はライターとして活動中。趣味は読書と財テク、アニメ鑑賞。蔵書は3000冊あったが、結婚してから嫁に本を増やすことを禁じられる。財テクに関しては株式投資を十数年、去年からFXはじめました。