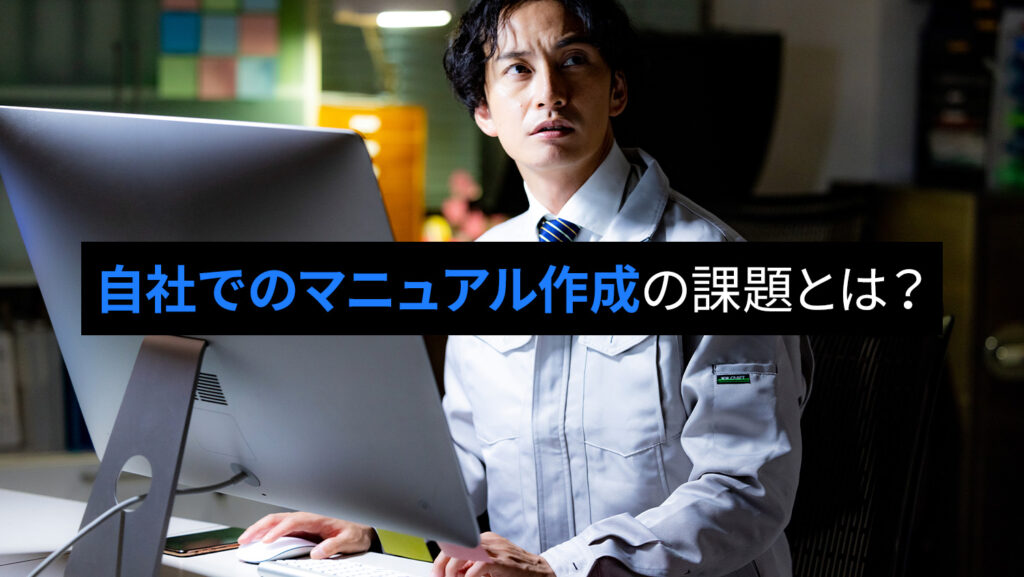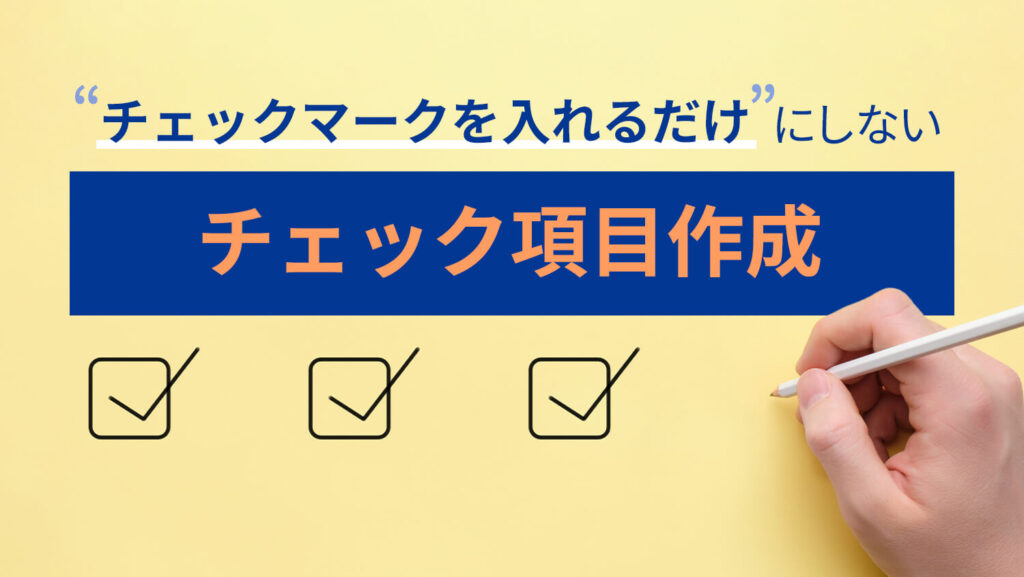目次
製造業でマニュアルが求められる理由

なぜ、製造業では作業⼿順書(以下、マニュアル)が必要と⾔われるのでしょうか。作業者に仕事を効率良く教えるためでしょうか。それとも、ISOやIATFといった国際規格で求められているためでしょうか。どちらも正解ではありますが、マニュアルの本質は品質にあります。しかしながら、意外にもマニュアルを活⽤している企業は多くありません。⼀度作ったら指摘されるまで修正されない、いわば“死んだ⽂書”として埃を被ってしまうケースが⾮常に多いのがマニュアルの実態です。しかし、製造業においてマニュアルとは⼤変重要な役割を担うツールであり、⽇頃から活⽤される“⽣きた⽂書”でなくてはならないのです。マニュアルの本質を理解するためには、まず製造業に求められる品質について理解を深める必要があります。
マニュアルとは品質であることを知る

品質とは、単純に製品が良いものであることを指すだけの⾔葉ではありません。顧客を満⾜させるための設計・サービス・製品、さらには価格、納期のことを全てひとまとめにした意味を品質と表現するのです。営業が顧客からヒヤリングした期待値を、設計部⾨が製品機能として反映し、製造担当者は顧客要求機能を果たし続ける製品を安定的に⽣産する責任を負います。顧客を満⾜させる3要素はQCD(Quality・Cost・Delivery)と⾔われますが、それはすなわち、バラツキがなく安定した製品を顧客に提供し続けることができる能⼒のことを⾔います。製造業においてマニュアルが必要な理由は、可能な限りこのバラツキをなくし、誰が作業をしても同じ品質の製品を⽣産するためです。そのため、マニュアルは⼯程のプロフェッショナルが作成し、伝承するための⻁の巻であることが求められるのです。
品質⽬線の製造マニュアルとは
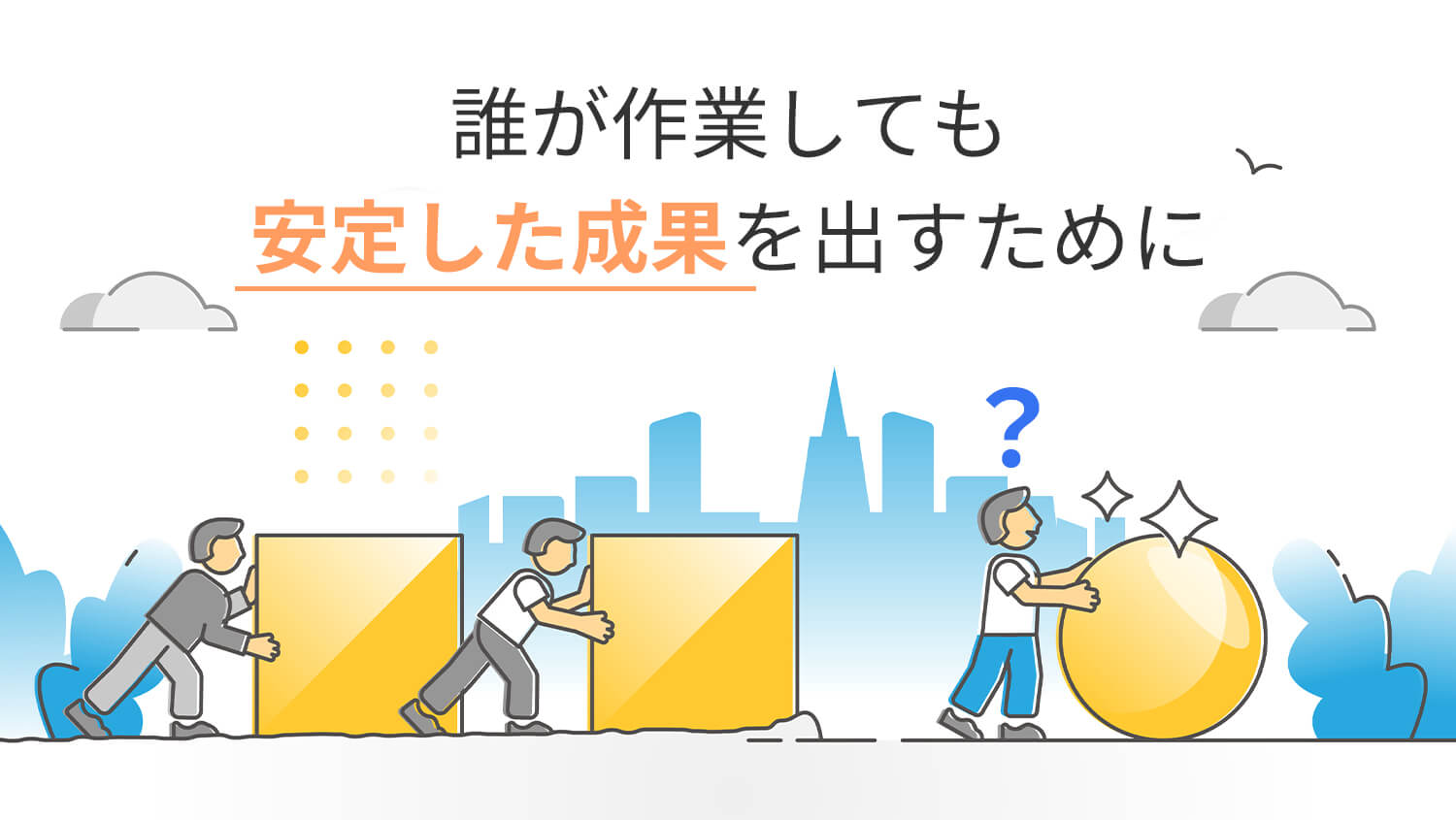
マニュアルによって精度を⾼められる作業はある程度定まっています。そもそもマニュアルとは作業者が読むために作られるものであり、⾃動⽣産ラインが安定して連続稼働している間はマニュアルを読む必要はありません。⾃動⽣産ラインへの材料供給や、設備の調整、メンテナンスや外観検査といった作業者⾃⾝が⾏う業務の精度を⾼めるために作られるのがマニュアルです。⼈が介在する作業は品質低下の⼤きな要因になりやすい性質があることから、読みやすく、わかりやすく、扱いやすいマニュアルが求められています。
品質を安定させるためのマニュアル作り

1. 曖昧表現を減らす
⽇本⼈の会話の特徴として「こそあど⾔葉」を多⽤することが挙げられます。これは指⽰語と⾔われ、⽇常的に頻繁に使われる便利な表現ですが、マニュアルのように正確に物事を伝える必要がある帳票においては推奨されません。例えば「隣のマシン」ではなく「⽣産マシン○号機」と表現すれば間違えることはありません。別の例として「マシン上部から材料を投⼊する」という書き⽅は望ましくなく、作業者が「マシン上部であれば⾼さは関係ない」と解釈することが予想されます。材料の投⼊時に落下の衝撃が懸念されることから、マニュアルには投⼊時の⾼さの規制を明確に記載する必要があります。このように、作業における決め事に具体性を増すことにより、品質は確実に向上していきます。
また、レシピ本に「塩コショウ少々」と記載されていることに違和感を覚えた経験はありませんか?料理をしたことがあれば、おおよそ指でひとつまみというイメージがつきますし、さらに詳しい⼈は0.2gだと理解することができます。しかし、マニュアルでは定量的ではない表現は避けなくてはなりません。材料投⼊マニュアルに『適度に投⼊すること』と書かれていたらどうでしょう。適度とは何kgなのか定まらず、担当者によって変わってしまいます。仮に材料を加熱する⼯程だとすれば、熱効率や保温といったパラメータに影響することとなり、製品特性にバラツキを⽣じさせてしまいます。そのような品質的バラツキを防ぐためにも、定量的な指⽰をする必要があるのです。
2. 熟練者と新⼈作業者のギャップに配慮する
マニュアルは熟練作業者や該当作業に精通した管理者が作成します。そのとき必ず注意しなくてはならないのは、熟練者と新⼈作業者の経験や知識のギャップによる解釈の違いです。これは実例ですが「設備周辺の掃除をすること」とマニュアルには記載されていたケースがあり、現場のルールを熟知している作業者はホウキとチリトリで掃除をしました。しかし、とある新⼈作業者がどこからか掃除機を持ってきて、⽣産設備と共通したコンセントに差し込み電源を⼊れたところ、⽣産設備に瞬間的な停電が⽣じてしまい⼤量の不具合が発⽣しました。このように熟練者の常識と、新⼈作業者の常識の違いを考慮したマニュアル作成が不具合を封じ込める品質的観点をもったマニュアルとなります。従って、読み⼿を意識した表記・表現を使⽤することが必要なのです。
3. 作業時間の⽬安を記載する
マニュアルの役割は作業⼿順を指⽰するだけではありません。製造業はビジネスであり、作業者一人一人の⼯数が会社の利益に結びついています。そのため、マニュアルには作業の⽬安時間を記載することが⼤切です。マニュアル通りに作業を⾏うことで、同じ出来栄えの製品を同じ時間で⽣産することができれば、そのマニュアルの完成度は⾮常に⾼いと⾔えるでしょう。逆を⾔えば、同じマニュアルを参考にしているのに作業が統⼀されていなかったり、作業時間に⼤きなバラツキが⽣じていたりする場合には、マニュアルを⾒直さなくてはなりません。顧客満⾜のためには、納期的品質にも配慮した作り込みが重要となってきます。
4. 関連帳票には正しい名称を記載する
『外観作業⼿順書を参照すること』という記載に従って外観作業⼿順書を探してみたけど、そんな名前の帳票が⾒つからず、マニュアルの作成者に問い合わせてみると『外観作業指⽰書』という帳票を指していた……ということが実際に起こり得ます。さまざまな帳票がデジタル化され、関連帳票を社内データベースから検索することができるようになった⼀⽅、関連帳票の名称を少し間違えてしまうだけでロスの原因につながるようになりました。時間的ロスが重なり作業者が仕事に追われ、正確性を失うというのも品質を低下させる要因となります。⼀⾒、作業とは関係のないと思える記述が、作業者の時間や精度を損なわせることにつながるのです。
5. 直感的な理解に配慮する
仕事だからといって膨⼤な量の⽂字を読むことを受け⼊れられる⼈ばかりではありません。むしろ、⻑い⽂章を読み、短時間で理解できる⼈の⽅が少ないでしょう。しかし、作業を⾏う上でマニュアルを読まないわけにはいきませんし、マニュアルには良い製品作りのためのノウハウが詰め込まれています。品質維持・向上のための読みやすいマニュアルにするためには、⽂字数を減らしながら、理解しやすさを向上させる⼯夫を盛り込まなくてはなりません。そのための強⼒なツールが写真と動画です。⽣産⽤ツールとしてスマホやタブレットを導⼊する企業が増えると共に、作業マニュアルのデジタル化も進んでいることをご存じでしょうか。ペーパーレス化だけでなく、読むマニュアルから真似るマニュアルへと、マニュアルも時代と共に移り変わっています。熟練者の作業をさまざまな⾓度から撮影した動画を編集し、カンコツ作業のような細かなノウハウや注意点をハイライトすることにより、⽂字を読むよりも早く正確に理解し、作業の統⼀化に役⽴てることができます。仮にデジタル化が未導⼊で紙のマニュアルを使っている企業であっても、写真の量やコメント、強調を増やし、作業の説明に具体性を増すことで直感的な理解に配慮することができます。
品質とはバラツキを減らすことであり、バラツキを減らすためにマニュアルがある

数字的なバラツキ、作業的なバラツキ、環境的なバラツキなど、⽣産活動における私達の⾝の回りにはさまざまなファクターが存在しています。それらが影響し合った結果として特性や⼨法にバラツキをもった製品が作り出され、ときに不具合が⽣じることがあります。不具合を避けるための究極的な理想はあらゆるバラツキをゼロにすることであり、マニュアルはバラツキを軽減させる強⼒なツールです。そして、マニュアルとは企業のノウハウが詰め込まれた財産なのです。書き⼿と読み⼿のギャップが少なくなる表現と⼯夫を⼼がけ、品質維持・向上に活⽤できるマニュアルを作成しましょう。
マニュアルのソリューションにご興味がある方はこちらをご覧ください。
この記事を書いた人
みだん
製造業に製品検査、品質管理で15年以上従事する副業ライター。 2度の離婚、注文住宅を3度建てるなど波乱の人生を歩む。 3度目の結婚にてパートナーに恵まれ、最近生まれたばかりの子供にメロメロ。 趣味は浅く広いサブカル全般と国内旅行と子供の世話。 執筆歴は長いが副業として始めたのは極々最近。 得意ジャンルは製造業関連の他、アニメ・ゲーム・映画などのサブカルチャー、注文住宅、男女の恋愛観。