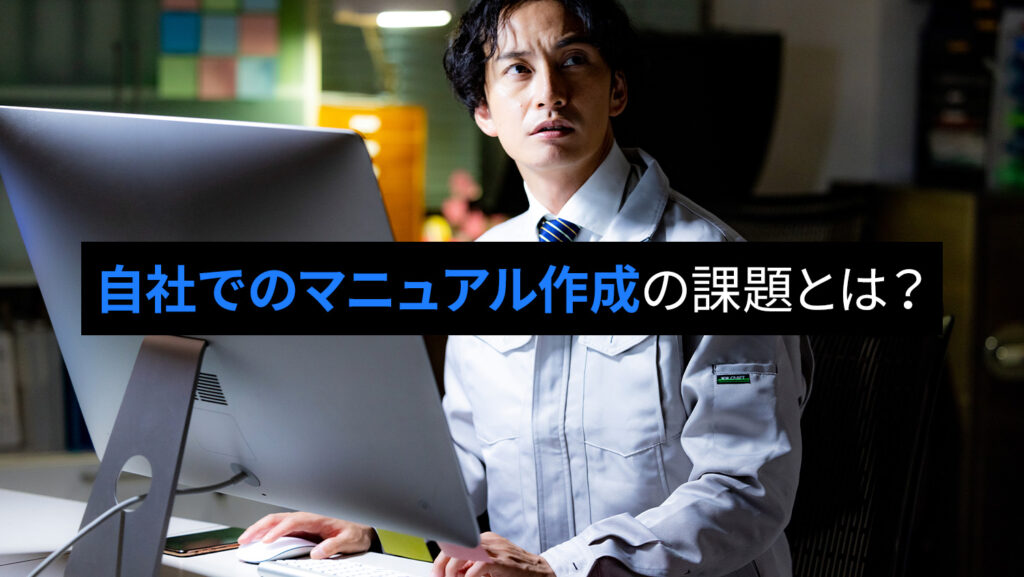製品の海外展開を検討すると、必要になってくるのがマニュアルの多言語化、翻訳です。
「製品のマニュアルを自社で翻訳した方がいいのか、翻訳会社へ依頼した方がいいのか」と悩まれる方は多いのではないでしょうか。
自社でのマニュアル翻訳は、コストを抑えられる、自社にノウハウを蓄積できるなどのメリットがあります。しかし反対に、時間がかかる、誤訳のリスクがあるなどのデメリットもあります。
翻訳会社へ依頼するとコストはかかってしまいますが、誤訳の不安が減り、マニュアルを自社で翻訳するために必要な人員、時間を削減できます。
どちらを選択するのかは、きちんと情報を見極めてから決めたいものです。
本記事では選択に役立つ「製品マニュアル翻訳時のポイント6選」「翻訳サービスの選び方」をご紹介します。
製品マニュアルを翻訳する方法は大きく2つある
製品マニュアルを翻訳する方法は大きく分けて2つあります。
「自社で翻訳する」「マニュアル翻訳会社に依頼する」です。
では、それぞれのメリット・デメリットを確認し、比較してみましょう。
方法1. 自社で翻訳する
メリットは、コストを抑えられ、自社製品の情報漏えいを心配しなくても良いという点です。また、自社で翻訳するので、翻訳に関するノウハウが蓄積できます。デメリットは、翻訳する人員の確保、翻訳にかかる時間、高いクオリティをずっと保ち続けるのは難しいという点です。また、専門家と違い、誤訳のリスクが伴い不安が残ります。
翻訳する際には、翻訳支援ツールが便利です。
翻訳支援ツールとはCAT(Computer Assisted Translation)ツールとも呼ばれ、翻訳すべきテキストだけをソフトに取り込み、翻訳したテキストを元データに上書きしたり、対訳を翻訳メモリとして蓄積し、次回以降の翻訳作業での参考資料にしたりすることができます。
ただしこういったソフトはあくまで翻訳を支援するためのもので、機械翻訳のように自動で訳文を用意してくれるものではありません。
方法2. マニュアル翻訳会社に依頼する
メリットは、マニュアルを自社で翻訳するためにかかるはずだった人員、時間を別の業務にあてられること、そして誤訳の不安が減ることです。
専門家が翻訳しているので正確な内容に訳してもらえますし、ネイティブの方にも違和感なく読んでもらえる表現にしてもらえます。
デメリットとしては、実際に依頼してみないとどれくらいの実力なのかわからないことや、内容が専門的な場合にそれを理解した翻訳者が翻訳するのか見えないことなどが挙げられます。
これは翻訳会社によって対応する分野・言語を絞ったり、翻訳者とは別に校正者を入れるといった体制をつくったりすることでそれぞれ差別化をはかっているので、それらを参考に選定を行うとよいでしょう。
製品マニュアルを翻訳する際の6つのポイント
製品マニュアルを翻訳する際の6つのポイントをご紹介します。
これは自社で行う場合も、翻訳会社に依頼する場合も同様に重要なポイントです。
ポイント1. 国ごとのマニュアル作成規定を確認する
マニュアル作成において注意していただきたいのが、各国が定めた規定です。
国外で製品を使用する場合には、マニュアルを使用する地域に合わせて規格の確認が必要になります。 日本、ヨーロッパ、中国を例に見てみましょう。
日本=JIS規格
日本産業規格、日本の産業製品に関する規格や測定法などが定められた日本の国家規格です。
ヨーロッパ=ISO/IEC 82079-1:2012
2012年よりヨーロッパで施行された国際規格です。欧州に製品を輸出する場合に準拠していることが必要になります。
中国=GB規格
中華人民共和国標準化法によって定められた技術基準で、日本のJIS規格に相当する国家標準規格です。
このように、製品の海外展開を視野にいれている場合は、各国の規定を守りながら翻訳をしなければいけません。事前にきちんと、マニュアルの翻訳を検討している国の規格を確認しましょう。
ポイント2. 用語とスタイルを統一する
マニュアル作成において、マニュアル全体で使用されている用語、スタイルを統一させることはとても大切です。
たとえば、「頻出の用語や専門用語の訳し方を決める」「スタイル、文体や記号、表現、表記のルールを決める」などがあります。こういった細かいことまで決めておかないと、「原文では同じ言葉・表記なのに訳文では変わっている」という状況になってしまいますし、そうすると訳文言語の読者が混乱してしまう・間違えてしまうといった問題に発展してしまう可能性すらあります。
そうならないように、訳し方、ルールはきちんと決めるようにしましょう。
ポイント3. 原文の時点で用語やスタイルを統一する
ポイント2.は翻訳時の注意点でしたが、これは原文に対してもいえます。
翻訳でいかに用語や表現や表記を統一しようと頑張っても、そもそもの原文で不統一があっては、限界があります。
大抵の場合、原文のマニュアルは自社で作成しているでしょうから、原文のマニュアルを執筆する段階で翻訳を見据えた用語や表現の統一を意識することも重要です。
ポイント4. 業界に精通した翻訳者が翻訳する
業界に精通した翻訳者でないと、一般名詞に見えるが実は固有名詞であるといったものや、業界によって特別な意味合いをもつ言葉などを誤訳してしまう恐れがあります。
翻訳会社の選び方については、「マニュアル翻訳会社の5つの選び方」で詳しく説明します。
ポイント5. 翻訳の対象範囲を決める
社内の翻訳担当に任せる場合でも、翻訳会社に依頼する場合でも、翻訳が必要な・不要な範囲がどこかは明確に指定しましょう。
そうしないと、不要な部分まで翻訳してしまって余計な工数・費用がかかってしまいます。
逆に、翻訳が必要だった範囲を誤って不要と指定してしまうと、後々で再度翻訳の追加依頼なども必要になり、これも余計な工数・費用がかかってしまいます。
ポイント6. スケジュールを決める
翻訳対象の文字数(ワード数)で、おおよその翻訳作業日数は試算ができます。
翻訳を開始する前に、いつ頃翻訳が完了し、いつからその訳文のチェックを開始して、いつまでに翻訳を完成させるのかのスケジュールを予め引いておくことも大切です。
マニュアル翻訳会社の5つの選び方
マニュアル翻訳会社へ依頼するには、何を基準に選んだらよいのでしょうか。この章では「マニュアル翻訳会社の5つの選び方」をご紹介します。
選び方1. 依頼したい言語に対応しているか
言語面の確認は、最も大切な部分になります。
英語、中国語などのメジャーな言語以外の翻訳を依頼したい場合はきちんと確認が必要です。また、何カ国語くらいの翻訳に対応しているか、依頼したい言語に対応しているかなどは翻訳会社のホームページで「対応言語の一覧」を調べてみましょう。
翻訳会社によって得意な言語が異なりますので、実績などを参考にしてどの言語の翻訳が得意なのかの見極めも必要です。
選び方2. 得意なジャンル・分野は何か
言語と同様に、ジャンルにも得意・不得意があります。こちらも実績を確認して、依頼したいジャンルの翻訳経験があるか、得意分野なども調べておくと安心です。
選び方3. ネイティブチェックに対応しているか
翻訳会社によっては、翻訳のクオリティがあまり高くないケースもあるので注意が必要です。みなさんも、母語である日本語がおかしい表記になっている説明書を見ると、不信感を持ちますよね。
そのような翻訳にしないために、ネイティブチェック※を行っている翻訳会社を選ぶことも時として重要です。
※その訳文を母語としている人が読んでも違和感がないように文章をチェック・修正すること
選び方4. 対応面で信頼ができるか
頼まれたものをスピーディーに翻訳するだけの翻訳会社もあれば、細かい部分に気づき改善提案してくれる翻訳会社もあります。
「相談しにくいことでもはっきりと伝えてくれるか」「見積もりの内訳や作業スケジュールが明確に提示されるか」「不明点の確認など積極的にコミュニケーションを取ってくれるか」といった点も、実は翻訳の品質に直結する要素となり、選定の一つの指標になります。
信頼できる、評価の良い翻訳会社をさがしましょう。
選び方5. 工程別に担当がおかれる体制か
翻訳、編集、校正、それらの進行管理といった業務ごとに担当者がおかれていると安心です。
こういった体制をもつ翻訳会社の場合は、業務が分散されているため、キャパシティが大きく、細やかな配慮をしてくれる可能性があります。ボリュームの大きい案件や、どうしても急いでほしい案件などの相談がしやすいのは魅力的ですね。
製品マニュアルを翻訳するには翻訳会社への依頼がおすすめ
いかがでしょうか。本記事では「製品マニュアルを翻訳する際の6つのポイント」「マニュアル翻訳会社の5つの選び方」をご紹介しました。
製品の海外展開には、マニュアルの多言語化、翻訳がかかせません。
国ごとの規定を守りながら、専門用語も含めてネイティブの方が読んでも違和感なく理解してもらえる文章を自社で翻訳するのはとても大変なことです。誤訳があれば取引先やユーザーからの信頼は簡単に失われてしまいますし、誤訳などの問題が起きないとしても、それだけの翻訳を行うリソースが割かれてしまいます。
それならば、コストはかかってしまいますが専門の翻訳会社に依頼し、人員と時間は自社のパフォーマンスを上げるために使う方が効率的です。
本記事でご紹介した選び方などを参考にして信頼できる翻訳会社を選び、積極的にマニュアル翻訳を依頼してみてくださいね。
技術翻訳のソリューションにご興味がある方はこちらをご覧ください。
この記事を書いた人
編集部