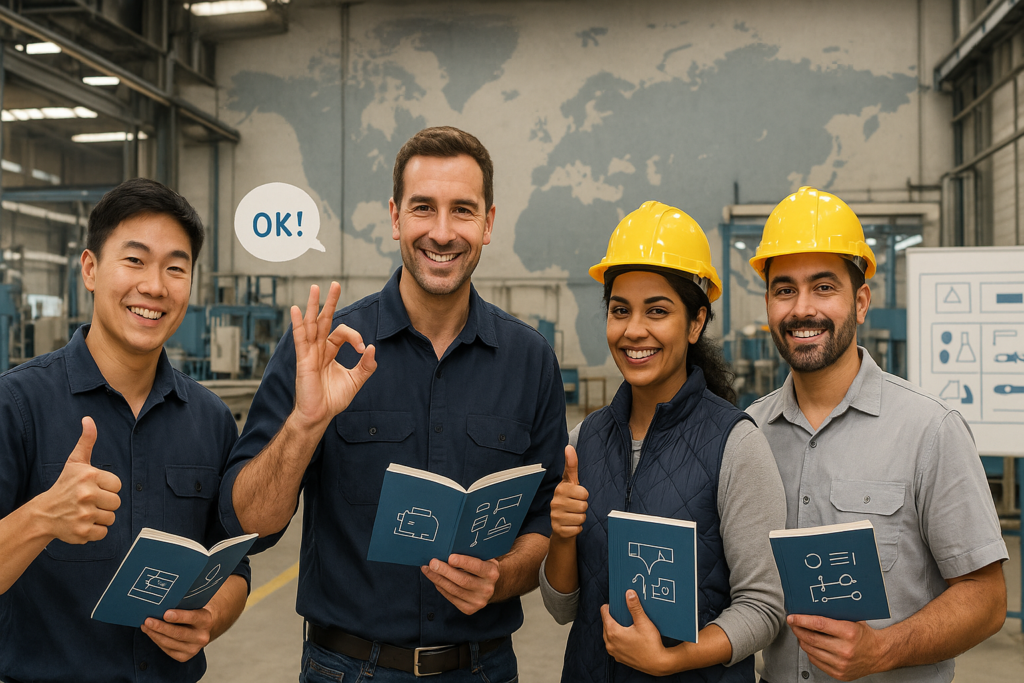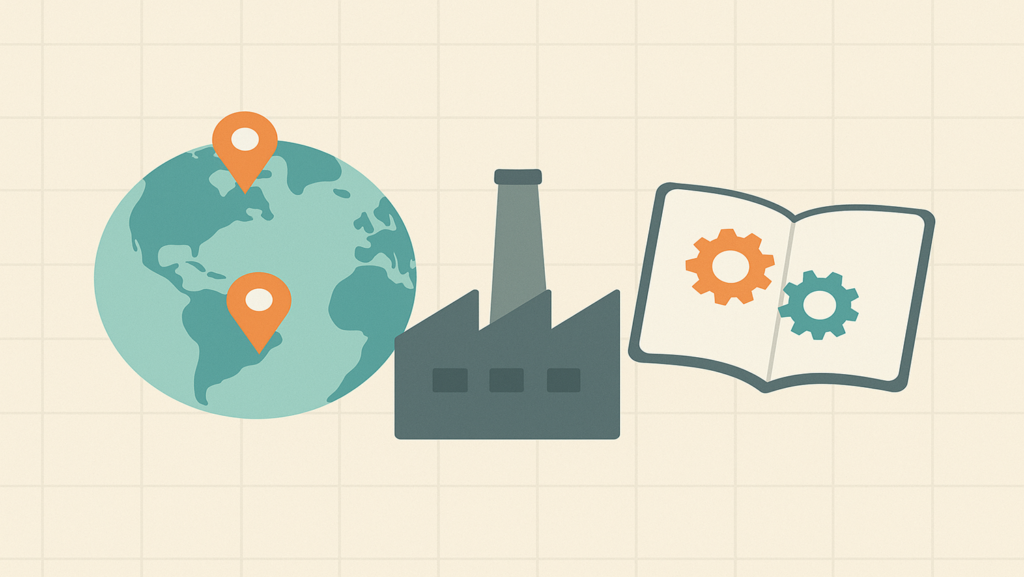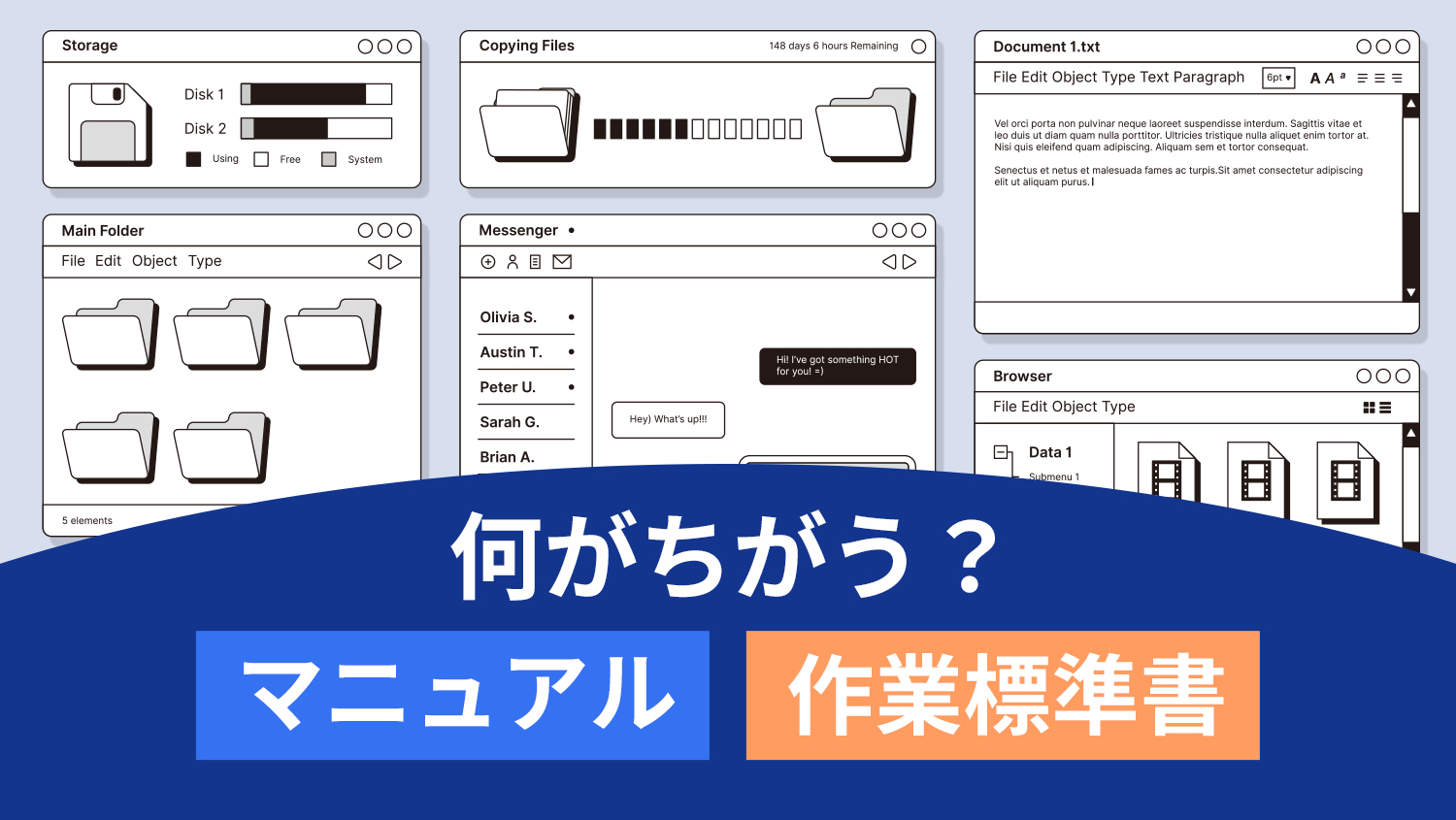
製造業で働き始めたばかりの方で、作業標準書という言葉を聞いたことはありますか?
- 一般的なマニュアルと何が違うの?
- 作業標準書って必要なの??
このように、お悩みではないでしょうか。
製造業では、当たり前のように使われる「作業標準書」という言葉。初めて、製造業で働く方にとっては、どういった内容なのか理解できませんよね。
そこで、この記事では、製造業で働き始めたばかりの方やこれから製造業で働く予定の方に向けて「作業標準書とは?なぜ必要なのか、具体的にどのように活用すればよいのか」をお伝えします。
また、一般的なマニュアルと作業標準書の違いについても、解説します。
この記事を読んで、作業標準書の正しい活用方法を身に付けましょう。
製造業で使用される作業標準書と一般的なマニュアルには違いがある

製造業で使用される「作業標準書」とは、一体どのようなものなのでしょうか?
作業標準書といっても、会社によって呼び方が複数存在します。とくに多く使われているのが、SOPといった呼び方です。SOPとは、Standard Operating Proceduresの略で、頭文字をとってSOP(エスオーピー)と呼ばれます。SOPと作業標準書は、同じと思って問題ありません。職場や会社などで呼び方が異なりますが、基本的な内容は変わらないからです。
作業標準書と呼ばれるマニュアルは、一般的なマニュアルとは少し違いがあります。どういった違いがあるかを簡単に説明します。
| 一般的なマニュアル | 業務全体の流れやノウハウをまとめたもの
仕事をする上で知っておくべき知識や進め方などが書かれている 製造業に限らず、いろいろな仕事で必要とされている |
| 作業標準書 | 各作業工程の具体的な作業手順をまとめたもの
作業者が、作業する上で守るべきルールやコツをまとめている 機械の操作方法や、使用する器具・工具など細かな手順が記載されている |
業務全体の流れやノウハウを理解するためには、一般的なマニュアルが必要です。
ただし、各作業工程の具体的な作業をするためには、作業標準書が必要になってきます。
製造業で作業標準書が必要な理由

製造業で大切なのは、「品質の一定化」です。さまざまな人が一緒に働く製造業では、各作業工程の作業標準書が「品質の一定化」を実現するための役割を果たします。
たとえば、3交代勤務制をとる工場では、時間帯によって作業する人は変わります。作業する人が変わっても、製造する製品の品質は一定に保つ必要があります。一定の品質を保つために、作業標準書を使用して同じ作業を行うようにする必要があるのです。
また、新しい作業者が加わっても、同じように作業できないといけません。新人作業者に正確に指導・教育するためにも、作業標準書は必要です。文書化していないと作業の内容を正確に伝達できない可能性があるからです。
そのため作業標準書は、製造業にとって非常に大切な役割を担っています。
製造業で作業標準書があることで得られる効果3つ
製造業では、作業標準書を作成し、活用すると、以下のような効果が得られます。
- 業務の効率化
- クレームの削減
- 人材教育の時間短縮
それぞれ具体的にどのような効果があるのか詳しく解説します。
業務の効率化
経験が浅い従業員では、業務を効率的にこなすのはなかなか難しいでしょう。
その点、作業標準書があると、業務の流れを理解しやすくなります。作業の手順が明確になるからです。そのため、作業の途中で迷ったり、悩んだりする時間がなくなり、結果的に業務効率化につながります。
また、ベテラン作業者が不在の場合でも、作業標準書があれば、作業内容を文書で確認できるので、業務の属人化を防げます。
クレームの削減
クレームは、品質に不具合があった結果、引き起こされるものです。
作業標準書を使って、誰が作業しても一定の品質を維持できるようになれば、クレーム削減効果も期待できます。
たとえば、機械の操作でも順番を間違えると仕上がりに影響する可能性があります。作業標準書で機械操作の順番を明確にしておけば、誰が操作しても同じ順番になり、結果的に品質を一定に保つ効果があるのです。
クレームを削減するためにも、作業標準書で品質を担保することは重要なのです。
人材教育の時間短縮
作業標準書を新人教育などに取り入れると、必要な時間の短縮につながります。
まずは作業標準書を読んでもらうことで、基礎知識を身に付けられるからです。知識が身に付いていれば、実際に作業の説明がスムーズに行えます。教育を受ける側も、より内容を理解できるでしょう。
作業標準書を読むと、新人作業者にもやり方を理解してもらいやすいので、効率的に教育が進められます。異動や退職に伴う引継ぎにも活用できます。
製造業で作業標準書を活用する具体的な方法
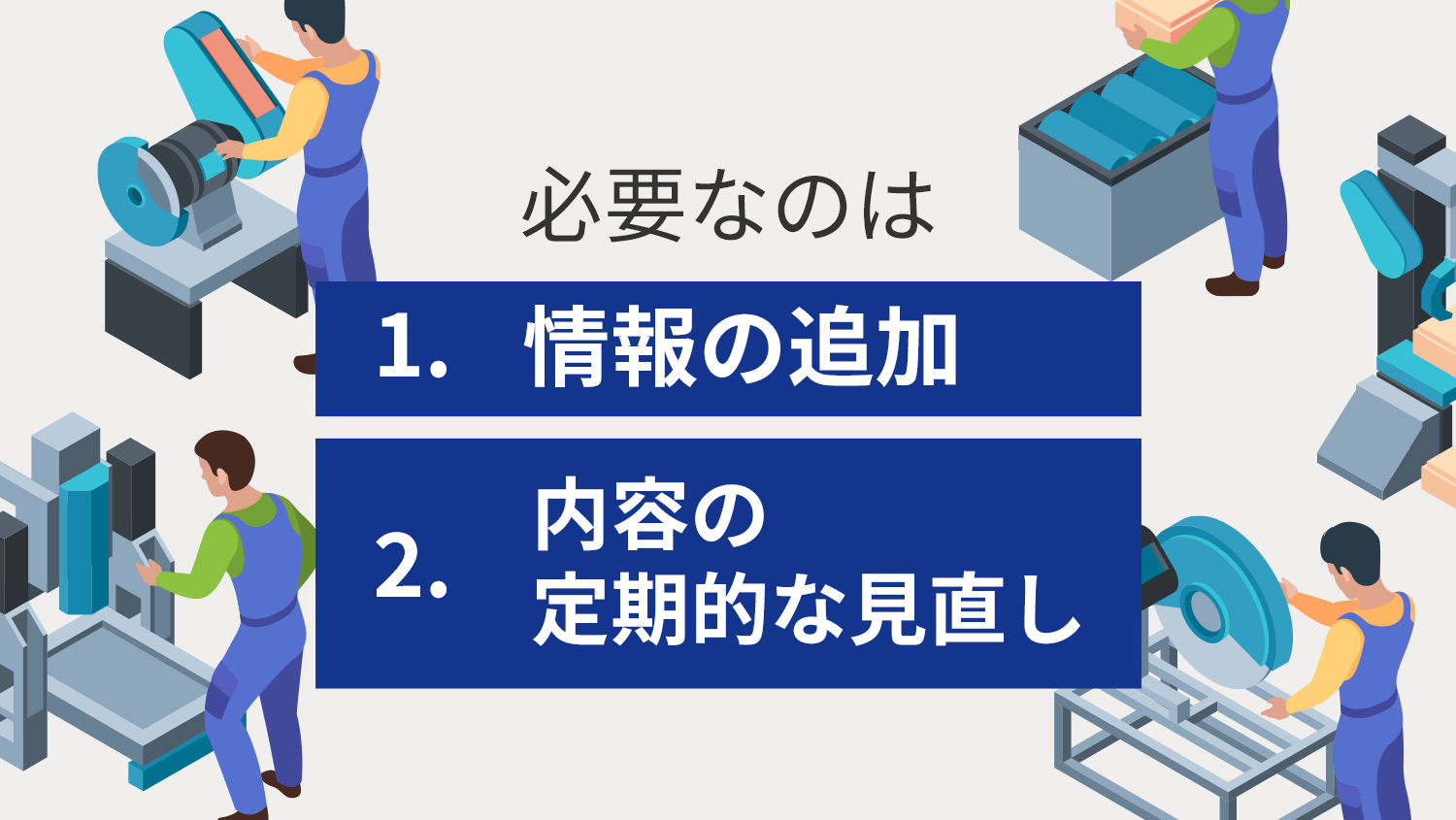
作業標準書は、さまざまな製造業で多く取り入れられています。
すでに、作業標準書を完備している工場も多いのではないでしょうか。作業標準書が完備されているのであれば、しっかりと内容を読み込み理解しましょう。その上で、不明点などがある場合には教育係の方に質問をすると、より理解を深められます。
ここでは、より作業標準書を活用するための具体的な方法を紹介します。
- 必要な作業標準書は追加する
- 既存の作業標準書を定期的に見直しする
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 必要な作業標準書は追加する
あなたの日常業務のなかで、作業標準書がないけどあったほうがいいと思う作業はありませんか?
もしもあったほうがいいと思うのであれば、積極的に作業標準書を作成しましょう。自分自身で作業標準書を作成すると、より業務への理解が深まり、理解度もアップします。
作業標準書を新たに作成するときのコツは、以下を意識してください。
- 一文を短く、シンプルにする
- 図や画像などを利用しわかりやすくする
- 必要な内容だけを記載する
この点を意識して作業標準書を作成すると、他の人が見てもわかりやすい文書になります。
必要だと思う作業については、積極的に作業標準書を作成しましょう。
2. 既存の作業標準書を定期的に見直しする
現在、使用している作業標準書は最新ですか?最新版かどうかわかるように、版番号などをつけて管理するのがおすすめです。作業に変更があった場合には、常に改定して最新版にしておくのが大切です。
最新版の作業標準書でも、現在の作業内容と違いがある場合もあります。そのような場合には、なるべく早く作業標準書の改定が必要です。具体的には、1年に1回や、2年に1回など、期間を決めて、作業標準書の内容を見直しするといいでしょう。作業標準書の見直しは、業務内容の再認識にもなります。
今後も、一定の品質を保つために使用する作業標準書です。常に最新の状態を保つことで「一定品質」の製品の製造が可能になります。
製造業では作業標準書というマニュアルを活用して安定した品質を!
この記事では、なぜ製造業で作業標準書というマニュアルが必要なのか解説しました。
複数人の作業者が同じ作業をできるように作成された作業標準書は、手順に間違いがないか確認できる大切なマニュアルです。ひいては製品の「品質の一定化」の実現を可能にします。
ぜひ、品質が一定化した製品をつくるために作業標準書はどういったものか理解し、活用してください。
この記事を書いた人
河井 ひとみ
製造業の品質管理・品質保証に20年以上従事していた経験があるフリーライター。医薬品や化粧品の製造工場で働いていたため、GMPと呼ばれる「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準」に明るい。医薬品や化粧品を作るために必要な手順書や記録書についてわかりやすく解説します。プライベートでは子育てママのため、お片づけや時間節約術など主婦の悩みに関する記事の執筆もしている。趣味は、温泉巡りとサウナ。