
製造現場におけるマニュアルは「紙」が常識ですが、最近はクラウドで管理するマニュアル、デジタルデバイスで見るマニュアルなど多様化しています。
その中でも注目を集めるのが動画マニュアルです。気になっている方も多いと思います。
本コラムでは動画マニュアルのメリットや導入事例を紹介しています。
動画マニュアルがどのように製造現場で役立つのか?ぜひ参考にしてください。
動画マニュアルのメリット
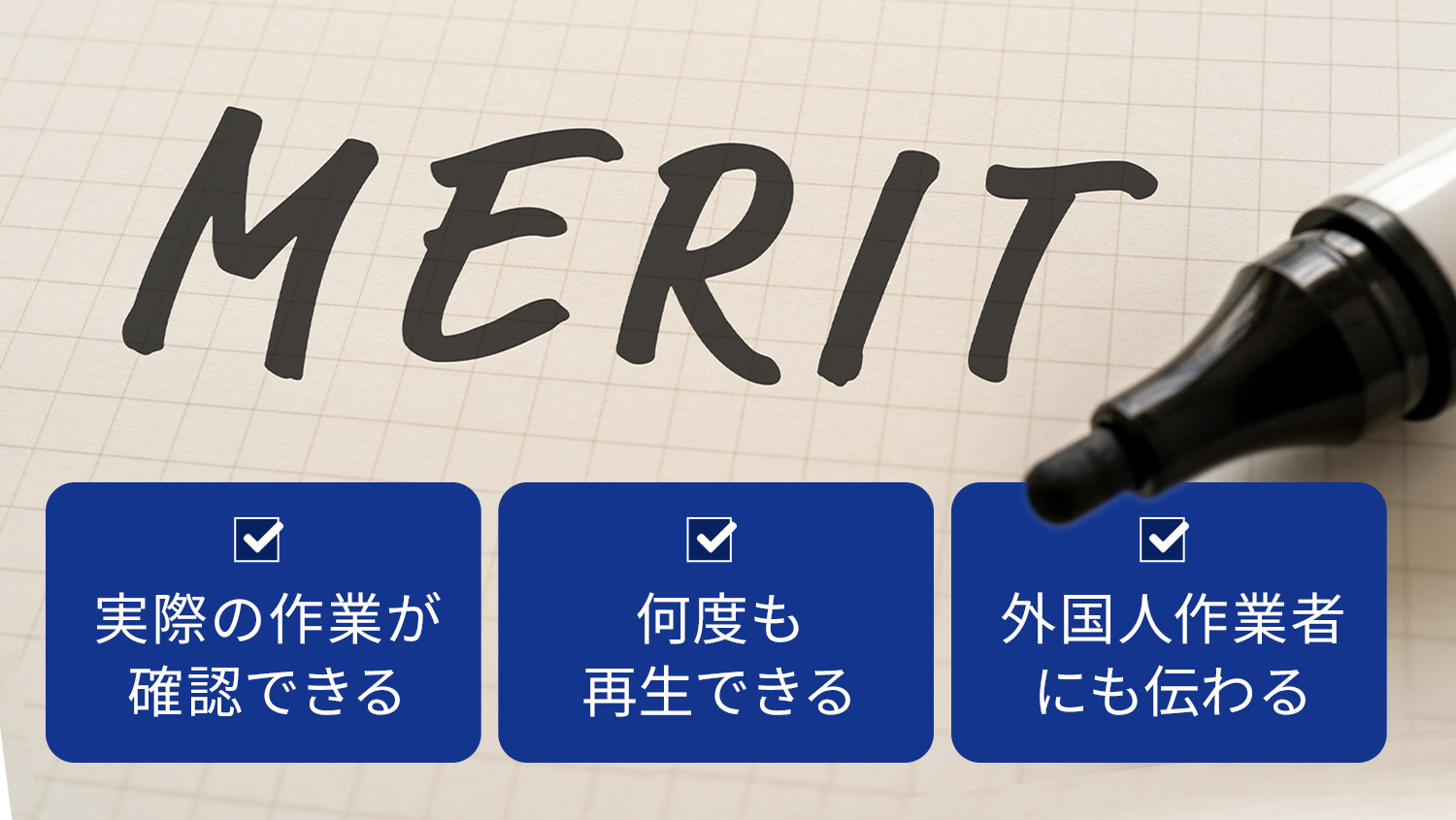
動画マニュアルの主なメリットは、以下の3つが挙げられます。
- 実際の作業を動画で確認できる
- 何度も動画を再生できる
- 外国人作業者にも作業方法が伝わる
実際の作業を動画で確認できる
動画マニュアルの強みは文章や口頭ではイメージしづらいことも、実際の作業風景を再生することにより、明確化させることができることにあります。
作業者へ作業方法をマニュアルで読ませる、口頭で説明する場合、聞き手ごとに異なる捉え方をする場合があります。
上司から口頭説明を受け、作業を実行した結果「違うんだよなぁ」と言われた経験はありませんか?
この「結果」を未然に防ぐには動画マニュアルが適しているといえます。
動画マニュアルの良いところは、作業者が受ける解釈の差異を極力小さくできる点にあります。
たとえば、ロール掃除ではウエスに溶剤や水を染み込ませる場合があります。マニュアルに「ウエスに水を染み込ませる」と書かれていた場合、作業者ごとに異なる解釈をする可能性が高くなります。
- ウエスを固く絞った程度の染み込み具合
- ウエスを軽く絞った程度の染み込み具合
- ウエスがヒタヒタになる程度の染み込み具合
作業者ごとに解釈に違いが出ると、製品の品質、作業効率に悪影響が出かねません。
このように抽象的で具体性のない文章や言葉だけでは、受け手により解釈が異なるというデメリットがあります。
しかし動画マニュアルを使うことにより、ロール掃除の例であればウエスの適切な扱い方を視覚的にわかりやすく伝えられます。
さらに動画では情報を音声とテロップにより、追加・補足することも可能です。
作業者ごとに違う解釈の溝を埋めることができれば、生産性や品質など製造業にとって大事な指標の向上につながります。
何度も動画を再生できる
動画のメリットに何度も確認ができるといった点もあります。人の記憶はそれほど優れたものではありません。口頭や作業方法を実演で説明されたとしても、一度見ただけでそれを完全に記憶しておくことなど不可能に近いでしょう。
また現場での教育は、業務と業務の間の短い時間に行われることがあります。指導者は他の仕事もあるので教育に時間をかけられないのが本音です。
指導者は限られた時間の中で口頭で教育をしますが、うまく伝わらない場合もあります。後日指導を受けた作業者の記憶漏れにより、間違った行程で進めてしまったり、指導者へ何度も質問することで生産性が低下してしまうこともあります。
しかし動画の場合は異なります。実際の作業方法を動画マニュアルとして残しておけば、動画を確認できるデバイスがある限り、実演や口頭で説明を受けても今ひとつ理解できなかったことや、忘れてしまったことでも何度でも動画マニュアルで確認することができます。
動画マニュアルを作成しておけば何度でも再生して確認できるため、指導者の負担を軽減することができます。ひいては生産性の向上につながるでしょう。
外国人作業者にも作業方法が伝わる
動画マニュアルは、言葉でコミュニケーションが図りづらい方にも伝わりやすい特徴があります。
ここで1つの事例をご紹介いたします。
ある化学メーカーでは、外国人作業者が従事しています。なかには日本語でコミュニケーションが図れない作業者もいます。
そのため、日本語で書かれたマニュアルでは理解ができず、規定とは異なるやり方で作業が行われ、ロスが発生していました。
そこで言語だけではコミュニケーションが図れない壁を打破すべく、動画マニュアルを導入しました。結果、企業内に作業工程や製造の細かいルールが浸透していきました。
外国人作業者の教育は言葉の壁が原因で不十分になりがちです。しかし、動画マニュアルを用いれば非言語での教育が可能になります。動画マニュアルを作成するさまざまなツールもあります。なかには字幕の言語を多言語に自動翻訳する機能を備えているツールもあるのでおすすめです。
動画マニュアルは昨今の多様性の社会での企業運営を円滑にするのにも力を発揮します。
動画マニュアルの導入例

動画マニュアルのメリットを説明してきました。ここからは実際にどのような動画マニュアルが企業で活用されているのか、事例を取り上げていきます。
VRを使った安全マニュアル
印刷メーカーである凸版印刷ではVR(ヴァーチャル・リアリティ)を使った安全マニュアルを提供しています。
安全道場VRでは、不適切なカッターの使用、エアーホース使用後の残圧処理を怠った場合などに起こり得る災害を作業者視点で体験ができます。
実際の作業を体験できるため、災害が起こる前の危険箇所や行動を事前に確認することができます。作業者が同じ動画を見るため、解釈の違いが起こりにくいです。
製造業に限らず、ある程度経験を積むと、慣れからくる注意不足が少なからず生じます。安全確認を怠った結果、大きな災害につながってしまったという話は報道でよく耳にします。安全道場VRは大きな災害につながりかねない危険箇所を事前に確認でき、対策に生かせる動画マニュアルの一つです。
参考:TOPPAN 安全道場VR
https://www.toppan.co.jp/solution/service/safetydojovr.html(2023年2月27日引用)
仕事の流れを解説した教育動画マニュアル
KURS(近畿生コン関連協議会)が作成したコンクリートの業務に関わる新人研修動画です。
コンクリートの製造から運搬、プラントに帰着後の洗浄作業など一連の工程を専門用語を用いずに、ドライバーや誘導員視点でわかりやすく解説しています。
たとえば、生コン車は納品後、生コンクリートをそのままにしておくと乾燥して固まってしまいます。生コン車の耐久年数を下げることにもつながるため、避けないといけないことです。
また前回使用した生コンクリートが残っていると、次に生コン車を使用する際に支障をきたすため、洗浄作業を行うことの大切さ、実際の洗浄方法が紹介されています。
自分が納得できるまで動画を再生できるため、業務内容への理解を深めることができます。そのため、入社したばかりでも作業内容への理解が早くなり、即戦力として働くことが可能です。
工程ごとに動画を分割しており、確認したい工程を都度確認できます。全体の流れを細かく分けて把握できるのも魅力でしょう。
参考:近畿生コン業界情報サイト「結」関連動画
https://www.yui-web.jp/movie/(2023年2月27日引用)
自動翻訳やイラストで外国人労働者にもわかりやすい動画マニュアル
2019年にパーソル総合研究所が行った「外国人雇用に関する企業の意識・実態調査」によると、外国人労働者を積極的に雇いたい企業が約70%でした。しかし、外国人労働者の育成には、言葉の壁があり、一人前の技術者を育成するのに時間がかかるのが課題です。
動画を使った業務マニュアルや作業マニュアルには、多言語に自動翻訳できるものがあります。自動翻訳機能があれば、日本語で作成したマニュアルでも外国人労働者の出身にあった言語で再生され理解されやすく、企業側で翻訳したマニュアルを新たに作成する手間がなくなります。
また、危険箇所や気をつけたほうがいいところは動画内で「注意事項のイラスト」や「危険マークのイラスト」を入れることで、相手に「やってはいけないこと」をわかりやすく伝えることができます。
このように外国人労働者を積極的に雇用したい企業にとって、動画マニュアルを導入することは打って付けだといえます。
参考:パーソル総合研究所 「外国人雇用に関する企業の意識・実態調査」
https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/data/employment-of-foreigners.html(2023年2月27日引用)
動画マニュアルを課題解決に役立てよう

動画マニュアルのメリットをおさらいします。
- 実際の作業を動画で確認できる
- 何度も動画を再生できる
- 外国人作業者にも作業方法が伝わる
動画マニュアルのメリットに焦点を当て解説しました。必ずしも動画マニュアルは万能ではありません。ですが、事例にあったように動画マニュアルがさまざまな課題を解決するのに実際に使用されていることは事実です。貴社の課題を解決するのに動画マニュアルが役に立つのではないかと少しでも感じていただけましたら幸いです。
この記事を書いた人
村木
液晶関係の製造業に10年従事している現役オペレーター。2度のメンタル不調で休職になったが、自分の生活を見つめ直すことで復職に成功。休職がきっかけでライティングを始める。製造業の記事の他にフリーランス系の記事やクレジットカードに関する記事など、さまざまな記事の執筆を担当している。最近の悩みは、筋トレで太くなった腕を後輩が見て「ゴリラ先輩」とイジられること。










