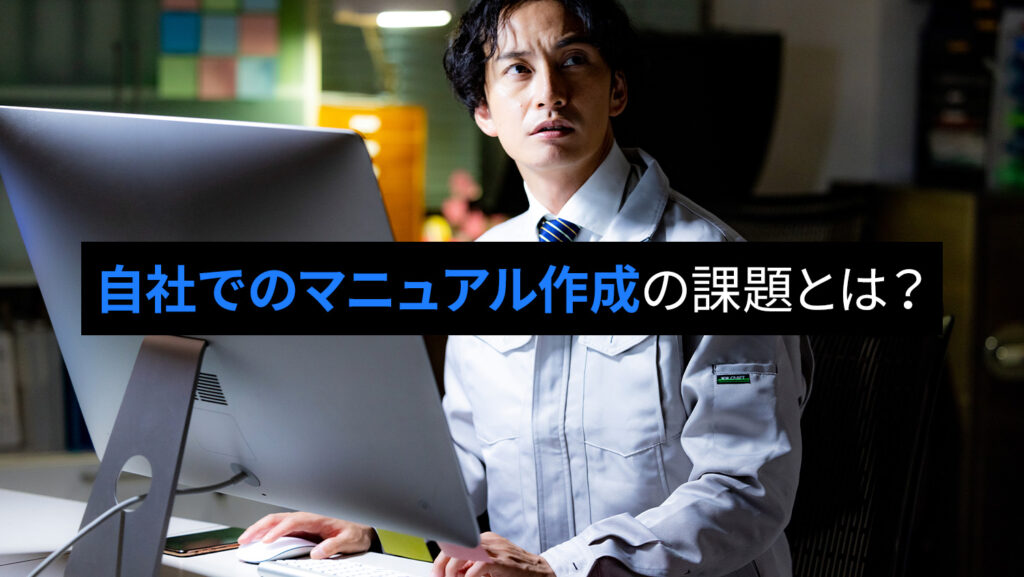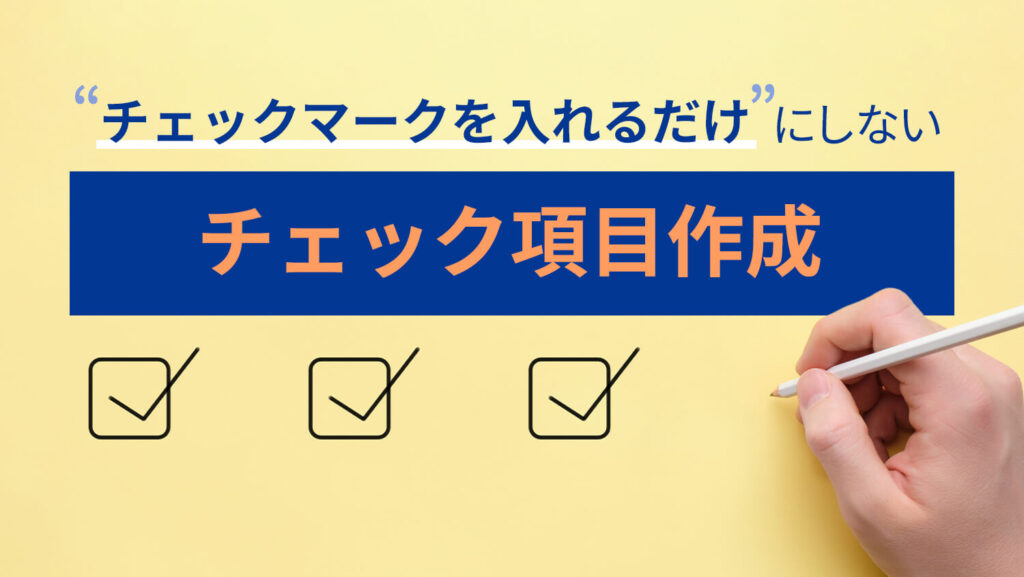製造業では、複数の工程を経て完成するものがほとんどで、安定した品質の製品を作り続けるためにはマニュアルは必須です。
品質安定のほか、業務の効率化やケガ防止のためにもマニュアルは重要です。
しかし、現場ではマニュアル作成に割く時間がなかったり、どんなマニュアルを作ればよいのかがわからなかったりすることも多いのが実情です。
そこで今回は、製造業におけるマニュアルの重要性やマニュアル作成時に起こりやすい問題と解決方法などについて解説します。
目次
製造業でマニュアルを作る4つの目的
製造業でマニュアルを作成する目的は、主に4つあります。
目的1. 製品の品質を安定させる
製造業において、製品の品質が安定していることは最重要項目です。
間違った手順で作業を行うと製品の不良率が上がり、会社全体の不利益につながります。
マニュアルを作成して作業を標準化することで、製品品質の安定を図ることができます。
マニュアルは、手順の誤りを最小限にするだけでなく、作業品質の平準化にも役立ちます。
製造業において、同品質の製品を大量に製造するためには、従業員の経験や熟練度に頼るやり方は通用しません。
誰にでもわかりやすいマニュアルがあることで、今日、初めて現場に入る新人であっても、ベテラン従業員と同じ品質のものを作り上げることができるようになります。
目的2. 教育コストを下げる
製造業において、新人の配属や異動などで、業務を一から教えなければならない機会は多くあります。
その際、先輩社員が新人につきっきりになると、本来、先輩社員が行っていたであろう業務を100%こなすことができません。
また、すぐに新人が仕事を覚えるとは限らないので、質問などがあればその都度先輩社員の作業の手を止める必要があるなど、非効率的になってしまいます。
このように、新人教育にはコストがかかるのが問題です。
マニュアルは、いわば「一番教えるのが上手な先輩」。
先輩社員がつきっきりで教えなくても、新人は作業を覚えられるというメリットがあります。
また、教える人によって作業内容が変わるというリスクもゼロです。
新人は業務でわからなくなったらマニュアルの該当部分を読めばいいので「今はちょっと聞きにくいな」と、タイミングを逃して聞けないということもありません。
迷ったらすぐに解決でき、業務の効率化につながります。
目的3. 業務スピードを上げる
マニュアルで「最も効率の良い作業手順」を示すことで、従業員は無駄のない作業ができるようになり、全員の業務スピードが上がります。
結果、短時間で多くの製品を製造できるようになるため、利益向上にもつながります。
目的4. 労災を防止する
マニュアルで危険箇所やケガをしやすいポイントを明記・共有することで、労災を防止することができます。
製造業の現場では、一歩間違えると大ケガをする危険性があり、最悪の場合は命にかかわることもあります。
マニュアルには、作業ごとの「危険なこと」を明記し、過去の事故事例などを記載しておくと、より「どういうことが危険につながるのか」がイメージしやすくなります。
また、マニュアルは何度も読み返すことができるので、定期的に確認する機会を設けて従業員全員で情報を共有し、危険防止への意識を高めるのにも役立ちます。
製造業でマニュアルを作る際の4つのポイント
製造業のマニュアルを作る際には、効果を十分に上げるためにしっかり押さえるべきポイントがいくつかあります。
ポイント1. 読む人の視点に立って作成する
マニュアルは「読む人・利用する人」が主役です。
作った人に聞かなければわからない言葉や作業が入っているのはNGです。
専門用語や略語はできる限り使わず、どうしても使う必要がある場合は、用語説明もあわせて載せておくようにします。
また、日本語以外の話者が多い、または多くなることが予想される現場では、使用されうる言語を把握し、何語まで対応するのかを検討しましょう。
ポイント2. スケジュールを意識する
マニュアルはスケジュールを決めて一気に作るのがコツです。
わかりやすいマニュアルは、文字の大きさやデザインなどの体裁が整っていて、全体を通して一貫性があります。
仕事の合間など「時間のあるときに作ろう」では、いつまで経っても完成しないばかりか、体裁などもズレてしまう原因になります。
マニュアル作成は締め切りを設けて、必ずスケジュールに組み込みましょう。
スケジュールを決める際には「新入社員が入る4月までに完成させる」など「いつまでにマニュアルが必要か」というデッドラインから逆算して作業を細分化することをおすすめします。
ポイント3. 完成後はマニュアルに沿って正確な作業ができるか確認する
マニュアルが完成したら「作業に詳しい人」「作業をまったくやったことがない人」の両者に確認をしてもらいましょう。
マニュアルは作業に慣れている人が作成するとは限りません。
記載漏れや無理のある動作などが記載されている可能性もあるため、作業に詳しい人に「本当にこのマニュアルで作業ができるのか」を確認してもらう必要があります。
逆に、作業に慣れている人の目線で書かれたマニュアルは、初心者にはわかりにくい可能性もあります。
作業についてまったく知らない人に、マニュアルに沿って作業を行ってもらい、完了できるのかまで確認すると安心です。
ポイント4. 完成後も更新を続ける
マニュアルは完成後も定期的に見直し「よりわかりやすいマニュアル」になるように更新し続けましょう。
マニュアルは「一度作って終わり」ではありません。
十分に確認をしたと思っても、人によってはわかりにくい部分が残っている可能性もあります。
マニュアルに沿って作業をする中で気づいたことを追記したり、より効率の良い方法が見つかったら内容を書き換えたりすることが大切です。
マニュアル更新のたびに時間を取られるのは会社にとって損だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、それはあくまでも一時的なものです。
マニュアルを改善することで、より短時間で高品質な製品が作れるようになれば、会社の利益になります。
製造業におけるマニュアルの作り方
業務マニュアルを作成する流れは、以下の通りです。
|
1〜8の手順について簡単に説明します。
1. スケジュールを決める
マニュアルが必要になる時期を決め、そこから逆算してマニュアル作成に取りかかります。
完成後も確認や修正が入ることがあるため、余裕をもったスケジューリングにしましょう。
2. 全体の構成を練る
マニュアルの流れや絶対に入れる内容など、全体的な構成を作ってから書き始めます。
行き当たりばったりで書いてしまうと内容に矛盾やズレが生じてしまう可能性があります。
3. 目次構成案を作成する
全体の構成で大まかな流れを書き出したら、さらに細かく具体的にして目次を作成します。
見ただけで調べたいことがすぐにわかるような目次構成を考えます。
実際の目次は最後にまとめて見直すので、ここでは案で大丈夫です。
4. 表紙を作る
必要なマニュアルがすぐに使えるよう、何について書かれているマニュアルなのかわかる表紙をつけます。
製品の写真や型番を書くなど、使いたいときに迷いなく手に取れるのが理想です。
最新版であることがわかるよう、更新日時も明記しておきましょう。
5. 本文を執筆する
目次に沿って本文を書いていきます。
情報を詰め込みすぎると判断に時間がかかってしまうので「1ページ1業務」にするとわかりやすいマニュアルになります。
難しい言葉は使わない、1文は長くし過ぎず40~60文字を目安にするなど「わかりやすさ」を意識しましょう。
6. テキストの装飾をする
大切なところやポイントがわかりやすいよう、テキスト(文字)の装飾を行います。
その際、色は2~3色までにし、シンプルにするのがコツです。
装飾も「重要なところはゴシック体」「危険なところは文字を赤くする」など、マニュアル全体で一貫してルールを決めておきます。
7. 写真やイラストを挿入する
写真やイラストを必要な箇所に挿入します。
文字だけのマニュアルはわかりにくいだけでなく、読むのが面倒で読み飛ばしてしまう可能性もあります。
動画を入れられる場合はぜひ活用しましょう。
8. 目次を作成する
マニュアルを辞書的に使えるよう「何が」「どこに」書いてあるのかわかりやすい目次を作成します。
以上、マニュアルの書き方手順1~8を簡単に説明しました。
製造業でマニュアルを作る際によくある4つの問題と解決策
製造業でマニュアルを作る際によくある問題を紹介します。
解決策もあわせて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
問題1. リソースが足りない
ここでいうリソースとは、人材を含めた経営財源のことです。
マニュアルを作ろうと思っても、従業員が今の仕事で手一杯で、マニュアル作成に人材をあてることが難しいケースは多いです。
【解決策】
一時的に経営面で不利になったとしても、コストをかけてマニュアルを作ることをおすすめします。
マニュアルを作ることで業務改善が進んで、従業員の仕事に余裕が生まれることも多いからです。
社内での解決がどうしても難しい場合は、アウトソーシングを活用する方法もあります。
作成を外部に委託したり、ITツールを上手に活用したりすれば、社内の負担を減らすことができます。
問題2. 統一感がない
マニュアルにまとまりがなく、体裁やデザインがバラバラで見づらいという問題があります。
これは、マニュアル作成担当者が複数いて、担当者間で連携せずに書いているケースでよく起こります。
【解決策】
複数の従業員に執筆を依頼する場合は、あらかじめレイアウトのフォーマットを決めておきましょう。
文章の書き方も統一するのがおすすめです。
たとえば、語尾は「です・ます」調と「だ・である」調のどちらにするかや、文字装飾のルールを決めておくといったことです。
マニュアル作成の取りまとめをする部署を作ると、最終チェックもしやすくなります。
問題3. わかりづらい
各部署の従業員が、それぞれの担当箇所についてマニュアルを作成すると、初心者の視点を欠いた内容でわかりづらいことがあります。
また、そもそも文章で説明をするのが苦手など、適性ではなかったというケースもあります。
【解決策】
完成後のチェックは必ず「その作業をまったくやったことがない人」にもしてもらい、マニュアル通りに動いてもらって、作業が滞りなく行えるかをチェックします。
もし、少しでもつまずいたり、迷ったりする場面があれば見直し・修正をし、修正後も同じようにチェックします。
文章の書き方が悪くてわかりづらい場合は、書き方のルールに沿って書いてもらうようにします。
マニュアルは小説ではないので、ある程度、型にはめて書けばわかりやすい文章が書けます。
問題4. 外国語への翻訳ができない
外国人従業員のためにマニュアルを外国語に翻訳したくても、社内では対応できないケースもあります。
【解決策】
翻訳を外部に委託する方法があげられます。
素人の翻訳や機械翻訳だと、原文の意図を正確に翻訳できない場合があります。そのために原文と訳文で記載内容が変わってしまうと、マニュアルの存在意義がなくなってしまいますし、トラブルのもとにもなります。
費用はかかりますが、翻訳会社など実力のある翻訳者に翻訳してもらった方がよいでしょう。
誰が見ても理解しやすいマニュアルを作って作業効率をアップさせよう
製造業でマニュアルを作るのには「品質の安定化」「教育コストの削減」「業務の効率化」「労災の防止」の4つの目的があります。
マニュアルを作る際には「読む人の視点に立つ」「スケジュールを意識する」「マニュアルに沿って確認する」「完成後も随時更新する」の4つのポイントを押さえると、わかりやすく、良いマニュアルになります。
マニュアルを作る際には、手順に沿って段階的に作成すると、効率良く、矛盾も生じにくいのでおすすめです。
マニュアル作成時には「マニュアル作りに割く人材不足」「統一感がない」「わかりづらい」「外国語の翻訳ができない」といった問題もあります。
それぞれの問題にあった解決策を取り、わかりやすいマニュアル作りを行いましょう!
「そうは言っても、自社で作るのはやっぱり難しそう」という場合は、アウトソーシングも検討を!
マニュアルのソリューションにご興味がある方はこちらをご覧ください。
この記事を書いた人
編集部